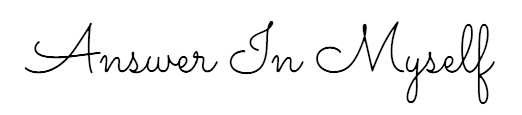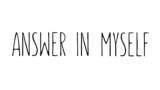長女の通う保育園では、今日が卒園式。
4月から年長さんになる長女は、保育園で一番年上となる意識があるようで
昨晩は突然「もう、おねえちゃんになるからお風呂一人で入る!」と言っていました。
まだまだ子どもなんだけれど
日に日に子どもではなくなっていく
嬉しいようでちょっと寂しい気持ちです。
長女が小学校にあがる2020年、学習指導要領改訂によりアクティブラーニング化が進みます。
アクティブラーニングというのは、主体的であることを軸とした学習。
以前こちらの記事でも少し触れました。

これからの時代は私たちの時とは違い
答えがない、多様な社会
そうなると大切になってくるのが自分の考えを持つこと。
大多数の中のひとりとして同調していたら
正解だけを求めていたら
「自分」が取り残されて苦しくなっていくのだと思っています。
そして私自身、これまで正解や答えを求めてきた部分がある。
でもそれは私自身の答えではなく
1+1は2であって、3や5にはならない
(数学的、物理的にはもちろん1+1=2でしかないと思いますが、つまりは他の回答が許されないような)
そんな感じの、自分の外側に合わせた正解だったように思います。
ちなみにこの私のブログタイトル
「答えは自分の中にある」
数年前から、私自身が感じている
最終的な正解は誰でもない、自分でしか出せない
という思いをタイトルにしています。
と、、、前置きがながくなりましたが
タイトルの家庭でもできるアクティブラーニングとは、日々の暮らしの中で小さな対話を重ねること
親としてはついつい子どもに対してあれやりなさい、これやりなさいというような行動を先回りした指示をしてしまいがちだけれど
(私もよくやってしまう。。。)
まずは子どもの今に目を向けて、指示ではなく、対話してみる。
例えばお茶がこぼれてしまったら
こぼれちゃったね、どうしたらいいと思う?って聞いてみる
そうすると子どもは自分で考え、ティッシュで拭いてみたり、何かしら自分でアクションを起こそうとする。
でもここで重要なのは
良い悪いで判断したり、話を進めないこと
家庭でできるアクティブラーニングと書くと
一見、子どものためにやるように思えるかもしれませんが、これって親自身も自分がどうするか、どう在るか考えるチャンスなのだと思う。
言葉がまだつたない年齢の子どもとの対話は時に理解不能で、親にとってはもはや修行に近い時もある気がするけれど(笑)
自分の子どもとはいえ産まれた瞬間から、物理的に他人であり、考えが同じとは限らない。
ルールやマナーなど、親として教えるべきこともあるけれど
考え方、感じ方は押し付けるものではないと思う。
良い悪いではなく、自分の考えを伝えあうこと
それは大袈裟なことではなくて
お互いにどんな風に思うのか、感じるのか
日々の小さな対話を繰り返すこと。
これから学校ではアクティブラーニングがどのように指導されていくのかわかりませんが、これが家庭でできるアクティブラーニング。
家族間だと余計に感情が出やすかったりして、話をややこしくしてしまいがちですが(^^;)
母、まだまだ修行の身です。